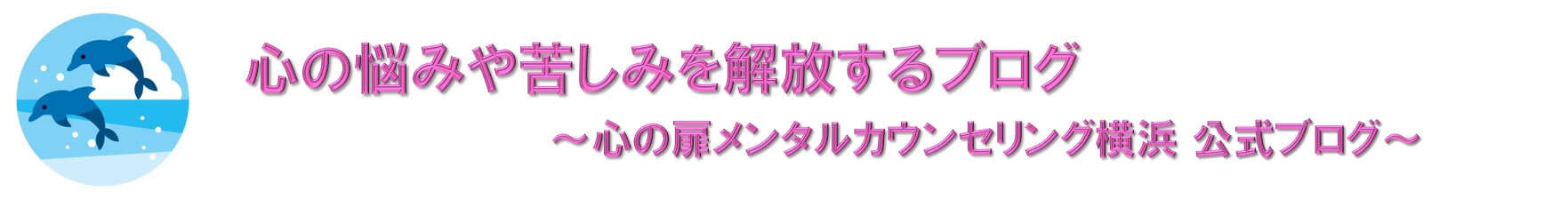カウンセラーの杉本もゆるです。
あなたの周りに、指示に従ってくれない人はいますか?
職場やグループのチームワークでの活動には、指示を出す人の存在が必要です。
しかし、全員が指示に忠実に動いてくれるわけではありませんね。
チームの中に一人くらいは、なかなか指示に従ってくれない問題児的存在がいると思います。
果たしてその人には悪意があるのかないのか、疑心暗鬼になりながら関わっている人も少なくないでしょう。
また、夫婦間や親子などでも、何かの指示を出すことは頻繁にあります。
今回は、指示に従わない人の心理や心の病気の可能性、対処法などについてお話ししていきます。
 レオ♂
レオ♂たしかに職場や学校など、どのコミュニティーにも「指示に従わない人」って一定数存在しているよね。管理者や責任者の立場からすると、とてもやっかいな問題になってしまうケースもあるけど、そもそも「指示に従わない人」はどんな心理でそうなってしまうのかな?そこには何か「深い理由」が隠されているような気がするね。
 ココ♀
ココ♀今回は「指示に従わない人」に共通する「7つの心理」や「5つの対処法」が詳しく紹介されているみたいね。またセルフカウンセリングで「指示に従わない人の心理」も自己分析できるから、自分の所属しているコミュニティーの管理者や責任者の人、またコミュニティーに不満のある人にもぜひ参考にして欲しいわね。それではもゆる先生よろしくお願いします!
【よく読まれているおすすめの関連記事】
同じ人間同士なのになぜか「ワンチーム」になれない!?「指示に従わない人」とは!?
指示に従わない人がいると、チーム全員にストレスがかかる
チーム全員が一丸となって目標に向かってまっしぐら。
いざこざもなくそれぞれが協力し合い、こなすべきことをこなしている…という世界はある意味夢のようなお話ではないでしょうか。
学生時代の部活動や学園祭などでも、なかなかチームに加わってくれなかったり、足を引っ張るような行動をとったりする人が、一人や二人いたと思います。
それは大人になっても同じ。
どんな職場やボランティア活動でも、すべての人が同じ熱量、同じ意志で動いてくれるなんて、ほとんどあり得ないことです。
もしも過去に一丸となって何かを達成した経験がある人は、それがとても良い思い出になっているでしょうし、現在そのようなチームに恵まれている人は奇跡とも呼べるような環境に心から感謝し、その仲間たちを大切にしましょう。
ただ、指示に従う人も指示に従わない人も同じ人間です。
きっと何かの事情があって指示に従わないのです。
単に反抗的な人だと決めつけるのではなく、その人の心理や自分の対応の仕方について考えることが必要です。
指示に従わない人の心理を学び、良い関係を作っていくために関わり方を改善させていきましょう。
「プライド」「頑固」「不信感」が原因!?「指示に従わない人」に共通する「7つの心理」とは!?
セルフカウンセリングで見えてくる「指示に従わない人の心理」
それでは、指示に従わない人の心理を7つ説明していきます。
この7つの説明を読み進めていきながら、セルフカウンセリングで自己分析してみましょう。
あなた自身に共通するものがあるかをイメージしたり、身近で当てはまりそうな人をイメージしたりするととても効果的です。
【指示に従わない人の心理①】信頼していない
指示を出した人のことを信用・信頼していないため、従おうとしません。
本人のプライドの高さや頑固な性格もありますが、指示を出した人の能力や技術、人間性に不信感を抱いていたり、関係が悪かったりするせいで指示に従わないのかもしれません。
【指示に従わない人の心理②】指示を理解できていない
指示の重要性を理解していないため、後回しにしたり自分なりのやり方で処理しようとしたりしてしまいます。
反抗心はないのですが、指示を出した人と出された人との意思の疎通がうまくできていない状況です。
【指示に従わない人の心理③】能力不足
指示に従おうとする意思はあるものの、本人の技術や知識不足のせいで指示通りにできません。
努力不足と言ってしまえばそれまででずが、本人ももどかしさを感じているかもしれません。
【指示に従わない人の心理④】自分のせいにされたくない
指示に従って失敗した時のことを考えています。
指示された方法で行った時に自分の責任になるのを嫌がるため、やれと言われたことをやらなかったり自分のやりやすい方法で行ったりします。
【指示に従わない人の心理⑤】忙しくて手が回らない
指示に従う意思はありますが、他のことに追われていてその指示にまでたどり着かない状況にいるのかもしれません。
それは業務過多な場合もあるでしょうし、本人自身や家庭などで何か大きな問題が生じている可能性もあります。
【指示に従わない人の心理⑥】納得できていない
出された指示に対して、効率が悪いと思っていたり必要性を感じていなかったりするせいで、指示に従おうとしません。
プライドが高く頑固な性格なため、自分自身がその指示にきちんと納得しないと動こうとしません。
【指示に従わない人の心理⑦】指示を出されたと思っていない
例えば、「あなたがやってくれると助かる」「〇日までが期限なんだ」などの話は理解できていても、自分に対してそれを要求しているとまでは考えが及ばず、自分への指示だと思っていないパターンです。
言い換えると、気が利かない人だと言えるでしょう。
セルフカウンセリングの自己分析はいかがでしたか?
自分や身近な人に当てはまる項目はありましたか?
自分や身近な人に当てはまる項目があった人は、指示を出す側と出される側の関係性を今一度見つめ直し、相手を誤解したり相手から誤解されたりしないように、できるだけ交流を深めることに努めましょう。
好き嫌いだけが理由じゃなく「心の病気」が原因かも!?「指示に従わない人」に隠された本当の真実とは!?
指示に従わない人の中には、心の病気を抱えている人もいる
指示に従わない人の中には、単純に指示を出してきた人が嫌いだからとか、めんどうだからなど反抗的な人もいますが、全てがそのような人なわけではありません。
一部には心の病気を抱えているせいで悪意や反抗心なく、自我が強いわけでもないのに、結果的に“指示に従わない人”というレッテルを貼られてしまう人もいます。
心の病気は目に見えないため、あらぬ誤解を受けてしまうこともあります。
例えば、アスペルガー症候群、ADHD、うつ病などが挙げられます。
アスペルガー症候群の人は主にコミュニケーションの分野に影響が出ることが多く、指示されたことを正しく理解できなかったり、曖昧な指示の出され方をされるとすべきことが判断できなかったりします。
そのため、アスペルガー症候群だと思われる人には曖昧な表現を避け、すべきことを明確かつ丁寧に教えてあげる必要があります。
きちんと指示を出して理解させてあげれば、指示通りに動いてくれるでしょう。
また、ADHDの人は衝動的に行動したり、集中力が続かなかったりすることがあります。
そのため、本人には悪意がないのに、やる気がないと思われてしまうこともあります。
ADHDだと思われる人には、こまめな声掛けがポイントです。
一度指示を出したら結果が出るまでそのままではなく、途中経過を確認してあげましょう。
指示は大きなものではなく、分割して小まめに出してあげる方が良いでしょう。
そうすると集中力も途切れにくく、指示通りに行動してもらいやすくなります。
そして、現代人に多いと言われているうつ病。
病院で診断され薬を服用している人も、自分では気づいていない人もいると思います。
うつ病になると様々なことへのやる気が低下し、集中力も持続しません。
判断力や問題解決能力も低下します。
今までやる気満々の頑張り屋だった人が、近頃姿勢が変わったり効率が悪くなったりした場合は、うつ病かもしれません。
周囲は温かい目で見守り、かつ、肯定感を上げるような言葉をこまめにかけ、サポートしてあげましょう。
「感情的」ではなく「理性的」なコミュニケーションが重要!「指示に従わない人」の「5つの対処法」を徹底解説!!
「指示に従わない人」にどう対処すべきか!?
心の病気が隠れているかどうかは分からないけれど、指示に従わない人がいて困っているという人は、以下に5つの対処法を説明しますので参考にしてください。
【指示に従わない人の対処法①】意見を聞いてあげる
指示に従わないのには何らかの理由があるはずです。
相手の意見に耳を傾けて従いたくない理由や従えない理由を優しく尋ねてみましょう。
そうすることで解決策が見つかるかもしれません。
また信頼関係も生まれ、今後指示に従ってもらいやすくなるでしょう。
【指示に従わない人の対処法②】明確に指示を出す
指示を出した側はすべてを把握していて、簡単なことだと思っているかもしれませんが、指示を与えられた側もそうだとは限りません。
曖昧な表現はできるだけ使わず、具体的に分かりやすく丁寧に指示を出してあげましょう。
【指示に従わない人の対処法③】目的まで説明する
ただやるべきことの指示だけを与えるのではなく、その目的や意味なども加えて説明しましょう。
表面的なことだけでなく内部的なところまで伝えることで特別感を与え、心にうったえかける様なイメージで指示を出してみましょう。
【指示に従わない人の対処法④】相手を持ち上げる
「君にしかできないと思うんだ」「あなただからこれを頼みたいんだ」などと選ばれた人だというイメージを持たせることにより、その人の肯定感が上がります。
言葉一つでその指示に対する熱意も変わってくるはずです。
【指示に従わない人の対処法⑤】小まめにコミュニケーションをとる
ただ指示を与え、指示をこなすだけの業務的な関係では、すべての人は快く動いてくれません。
褒められたい、助けて欲しい、などというその人その人の心の声に気づき声掛けしてあげましょう。
コミュニケーションを増やすことで空気感も良くなり、他の人のストレスも軽減されます。
上記のことに気を付けて、指示に従わない人とも良い関係を築けるように工夫していきましょう。
【まとめ】「指示に従わない人」だけを変えようとするのはNG!大切なことは「指示を出す側」の考え方から変える必要があるということ!!
指示に従わない人だけが悪いわけではない
指示に従ってくれない…と聞くと、従わない人が悪いように感じてしまいますが、原因は決して従わない人だけにあるわけではありません。
指示を出す側にも改善すべき点はたくさんあるのです。
人を変えることはできません。
変わってほしいと思うのなら、自分がその相手への関わり方を変えるしかないのです。
指示に従わない方が悪いと決めつけるのではなく、自らがコミュニケーションスキルを向上させたり、やり方を変えたりする必要があります。
時にはコミュニケーションセミナーやビジネスセミナーなどに参加してみたり、専門のカウンセラーからカウンセリングを受けて改善策を一緒に考えてもらったりするのも良いでしょう。
指示に従わない人のせいで大きなストレスを抱えてしまっている場合は、自分だけでなんとかしようと思わず、精神科や心療内科など医療機関を受診したり、定期的にカウンセリングを受けたりすることをおすすめします。
とにかく、大切なのはコミュニケーションです。
お互いが誤解なく良い関係でいられるように、効果的な工夫をしていきましょう。
あなたの気持ち、やり方次第で相手にちゃんと伝わりますよ。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
杉本もゆるでした。
心の扉メンタルカウンセリング横浜
筆:杉本もゆる
 レオ♂
レオ♂もゆる先生ありがとうございました!最後まで読んでいただきありがとうございます!あなたのお役に立てれば幸いです!良かったら「いいね」や「ツイート」などよろしくお願いします!!
 ココ♀
ココ♀ほかの記事もたくさんあるので読んでもらえると嬉しいです!無料メルマガもぜひ登録してみてください!只今プレゼントキャンペーン中です!▶ 詳しくはココをクリック!!